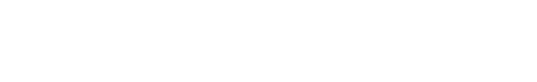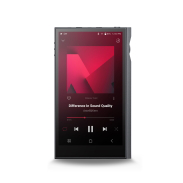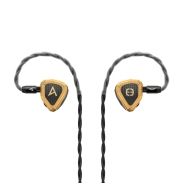1. ナンバーガール「BRUTAL NUMBER GIRL」(『SAPPUKEI』収録)
1. ナンバーガール「BRUTAL NUMBER GIRL」(『SAPPUKEI』収録)
- 小野島:
- まずはナンバーガールの曲からです。個人的に私が選んだ曲なんですが、これを聴いてショックを受けたというか、すごいなと思った思い出の曲です。ナンバーガールのメジャー2ndアルバム『SAPPUKEI』(2000)から「BRUTAL NUMBER GIRL」という曲を聴いていただきました。これはご存じの通り、向井さんと縁の深いデイヴ・フリッドマンがプロデュースで、彼のTarbox Road Studioで録られた最初のアルバムということなんですけど、これが実現した経緯というのは?
- 向井:
- 『SAPPUKEI』は、(デイヴ・フリッドマンとの)レコーディング自体としては2回目なんですね。その前に「DESTRUCTION BABY」(1999)という4曲入りのマキシシングルがあって、そのレコーディングを『SAPPUKEI』の1年前に行っているんです。ザ・フレーミング・リップスの『クラウズ・テイスト・メタリック』というアルバムを95年に福岡で聴いたんですが、この録音がデイヴ・フリッドマン。今でもザ・フレーミング・リップスは全部デイヴ・フリッドマンがプロデュースしているんですけど、このサウンドも曲もめちゃくちゃカッコいいし、ちょっと変なところもあって、すごくアグレッシヴで、特にドラムの音がすごく独特だなと感じたんです。それで、これは誰がやっているんだろう、と。バンドのレコードを好きになったら、プロデューサーとかエンジニア、レーベルとか、裏のクレジットとか音楽を聴きながらずっとたどっていったりしますよね。
- 小野島:
- そういうタイプなんですね。
- 向井:
- エンジニアの人は誰だとか、マスタリングは誰それだとか。この名前どっかで見たことあるな、ボブ・ラディックってなんか、どっかで見たなって、他のレコード引っ張りだして、ほら、やっぱそうやったとか。神経衰弱みたいな楽しみですか。このアルバムもボブ・クリアマウンテンか、とか。
- 小野島:
- やっぱりこいつかと。答え合わせのように。
- 向井:
- 確かにそのサウンドの傾向はそうだわとか、そういう楽しみがありますよね。それと同じように、誰がやっているんだとなって、エンジニア、produced byフレーミング・リップス&デイヴ・フリッドマン。エンジニア、デイヴ・フリッドマンと名前がインプットされたんです。その後、ウィーザーの2ndアルバム『ピンカートン』も同じくらいに出て、それも聴いて、このドラムの音むちゃくちゃカッコいいと。これは誰がやっているんだろうとまた裏返してみたら、デイヴ・フリッドマンだったんです。やっぱり、すごい好みのサウンド・エンジニアなんだと思いまして、我々ナンバーガールがその当時東芝EMIに所属していたんですが、自分たちの担当ディレクターの加茂啓太郎が当時手がけていたペンギンノイズというロック・バンドがデイヴ・フリッドマンにレコーディングしてもらったと聞きまして。加茂さんに、うちらもやらしてよって言ったんです。デイヴとはすでに1回やっているから、話が早いわけですよ。で、実現したという経緯ですね。
- 小野島:
- 音楽の聴き方っていろいろと人によって違うと思うんですけど、例えば歌詞に共感して聴くとかね。メロディがいいなと思いながら聴く人もいるだろうし。あるいは楽器のインプロがいいなと思う人もいるだろうし。向井さんはサウンドとか、どういう音で鳴っているかというのが気になる方ですか?
- 向井:
- そういうことも気になるし、例えばXTCの初期のギター・サウンドって、すごくギザギザしているというか尖って聴こえて、それがすごくカッコイイんです。どうしてカッコいいのかなと思ったら、アンディ・パートリッジのギターの弦、その下の方の細い弦である1、2、3弦を使ったAマイナーのコードは、すごく短い鳴らし方、かつ、短いスラップエコーというショートディレイがかかっている、うっすらと。その短い残響感と鳴らし方とギターの音づくりを含めて、ギザギザしていると思えるわけです。
- 小野島:
- 同じメロディと歌詞、コード進行であっても、それをどういうふうに鳴らして聴かせるかということで変わってくる。アマチュアで福岡にいらっしゃるときから、そういうことが気になっていた。
- 向井:
- 今いちいち考えたらそういうことになるという話で、聴いている時はわーかっこいい、光る、なんでだろうと思っているだけです。
- 小野島:
- なぜかっこいいんだろうと。
- 向井:
- そう。突き詰めて考えていくとそういうことなんですよね。やっている人の気持ちが入っているかどうかじゃないですかね。ナンバーガールの話じゃなくなるんですけど、シカゴ・ハウスってあるじゃないですか、初期の。
- 小野島:
- トラックス・レコーズとかの。
- 向井:
- あれは日本製の非常にチープなドラムマシンの打ち込みで作られている。しかも非常に簡単なビート。キックとハットと後ろの方でパーカッションがちょっと鳴っているくらいのが延々続くんですね。機械だからそれを打ち込んだら、誰が打ち込んでもキックの音は同じ音になるんですけど、なぜかね、トラックスの連中が一発ずつぶっとい指でブッブッブッって打ち込んでるその情念みたいなものが感じられるわけですよ。
- 小野島:
- ボタンを押すだけで情念が伝わりますか。
- 向井:
- 情念っていうのは絶対伝わると思っているんです。その音圧っていうのがすごくソウルフルで。機械だから無機質ですよね、本来。でもすごいソウルを感じる。
- 小野島:
- 野暮を承知でお聞きしますけど、その「情念」はどうやって音に定着させるんですか?
- 向井:
- それはキックドラムの音一発だけでそう感じるわけじゃなくて、やはりあのビートといろいろなシンセのフレーズだったり、曲の世界が合わさったりしていれば、作っている人たちの気持ちが届いてくると思うんですよ。キックの音にも加えて、俺の心臓の鼓動がこうなっているみたいな感じも私には届いてくるんですよ。
- 小野島:
- ご自分が音楽を作られるときには、そういう情念というかパッション、エモーションみたいなものを演奏に込めて、どうやってCDなりレコードなりという形でお客さんに届けるかということですよね。
- 向井:
- そういうことですよね。聴く側としてはそういうのが自分に届いてこないものはやっぱり聴くことはないですよね。
- 小野島:
- それはどこで分かれるんですか? 例えばフレーミング・リップスが、デイヴ・フリッドマンがやってなかったら違う聴こえ方になっていたかもしれない、もしかしたら向井さんの心には届かなかったかもしれない可能性もあるってことですよね。
- 向井:
- でも、フレーミング・リップスという人たちがいて、デイヴ・フリッドマンという人がいて、その人たちが出会った、一緒につるんだというのはやっぱり必要だったんじゃないですか。このフレーミング・リップスの音楽を作るにおいて。
- 小野島:
- 一体化したものであると。それも込みでフレーミング・リップスの音楽であると。
- 向井:
- 結局、その後20年以上デイヴ・フリッドマンと一緒にやっていますからね。
- 小野島:
- そういう意味ではナンバーガールがデイヴ・フリッドマンと組んでアルバムを作ったのも必然だし、デイヴ・フリッドマンの仕事を含めて『SAPPUKEI』というアルバムがある。
- 向井:
- そうですね。
- 小野島:
- 実際やってみてどうでした?
- 向井:
- スタジオが山の中にある山小屋なんです。レコーディングフロア、非常に天井が高い。1階2階とブチ抜きのフロアで、しかも小屋だから全部木造なわけですよ。そこでドラムを鳴らしたりピアノを弾いたりすると、木鳴りがするんですよね。木のアコースティックな残響がとてもいい響きがするわけです。それをそのままオーソドックスに録るんですけれど、その時点ですごくかっこいいドラム・サウンドになっている。ギターやベースは小さいブースに入ってセパレートで録るんですね。録りはけっこうオーソドックスなんですよ。
- 小野島:
- スタジオ自体、いい音が鳴るようになっているような環境で、作為を加えないでもああいうカッコいい音が録れる。
- 向井:
- そこでレコーディングし終わったものを、ミックスダウンの時のエンジニアリングでさらに例えば過激にしたり、より生々しくしていったりするわけですね。特にこのリップスのレコードがすごく極端な音作りしているから、そういうふうにしたいとリクエストした。けっこう思いつきなんですよね。もっとこうビリビリというイメージの伝え方をしていて、You know びりびり? What?って言われて。ビリビリはビリビリ。OKって。通じるんですよ。そしたらグラフィックイコライザーの全部上げてみるかみたいな。当然オーバーロードということでひずむんですけれども、これはいいと思ってがっと極端にやってみるとか。エンジニアの人ってちょっとずつやるんですけど、デイヴはそれを極端に全部上げればいいっていうタイプなんですよね。
- 小野島:
- 極端にがーっと。
- 向井:
- ちょろちょろやらない。ぶいっとこうなったら歪んだ、OK。みたいな感じでしたよ。
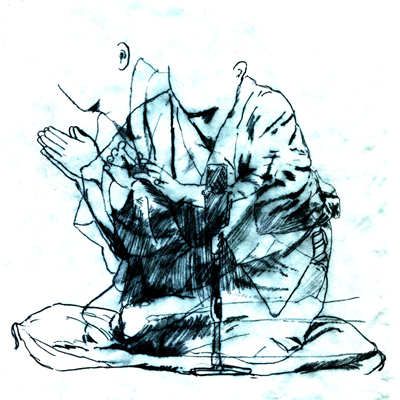 2. ZAZEN BOYS「泥沼」(『すとーりーず』収録)
2. ZAZEN BOYS「泥沼」(『すとーりーず』収録)
- 小野島:
- これだけしゃべってまだ1曲しか聴いてないんですけど(笑)、次がZAZEN BOYSの最新アルバム『すとーりーず』から聴いていただこうと思います。このアルバムからハイレゾで配信が始まっていますが、普段はアナログ盤でしかお聴きにならないそうですね?
- 向井:
- はい。
- 小野島:
- レコーディングの環境はデジタルを揃えてらっしゃるんですよね。アナログでレコーディングするのは難しいわけですか?
- 向井:
- 難しいですね。というか、面倒くさい。昨今アナログ・レコードのリリースも多いし売り上げも高まっていますし、確かに私もアナログ・レコードで聴きます。アナログでレコーディングしたものをアナログでプレスしてマスタリングしてカッティングすれば、すべてアナログだから良いのは当たり前なんですけど、デジタルでレコーディングしたものをアナログ化するっていうと、いちどデジタルとアナログDA変換が入りますよね。アナログの方が、音がいいという言い方をする場合もありますけども、厳密にいえばそうじゃないと思う。デジタルをアナログに変換しているから、手が加えられているというか、そこにいちど余計な作業が入っているふうに思えるんです。
- 小野島:
- つまり現代のデジタル・レコーディングのものをアナログで出すのはどこか不自然というか。デジタル・レコーディングのやつはデジタルで聴くのがいいということですか?
- 向井:
- いいかどうかはわからないですけど。マスタリングの話になってくると思います。マスタリングというのはレコーディングした音源をCDというフォーマットにするための盤に刻み込むためのとりまとめ作業、または配信向けにデジタル・フォーマットにするための作業になります。だいたいはCD用にマスタリングしたマスター音源を使ってCDにしたり、MP3にしたり、アナログ盤にしたりすることが多いと思うんですよ。これは予算も含めての事情もあって、それぞれのフォーマットに応じたマスタリングにすることが難しい。でも、『すとーりーず』はアナログ・カッティング・エンジニア(ケヴィン・メットカルフ)に頼んでアナログ用のマスタリングをしてもらったんですね。カッティングというのはレコードのプレスの原版を作る、溝に情報を刻み込むためのそのマスタリングです。そこでイコライザーを使うこともあれば、何らかのリミッターをかけることもある。その作業っていうのをちゃんとしてもらわないと、ちゃんとしたレコードにならないですよね。レコードって、すごいシビアだから。この作業をちゃんとしないと、いい音になりません。
- 小野島:
- つまりZAZENのアナログはそういう過程を経て神経を使って作られている。例えばハイレゾで配信したデジタルデータに関しては、レコーディングした時のままの音なんですか?
- 向井:
- CDとは分けて48kHz/24bitのマスターを作りました。
- 小野島:
- そのハイレゾ音源の『すとーりーず』から「泥沼」を聴いていただきましたが、これはまたすごい音ですね。
- 向井:
- バスドラムのマイク用の穴にずぼっと頭突っ込んで、ドラムの中で音を聴いているようなサウンドでしたね。ドッ、ドッっていう(松下)敦さんのキックドラムを直に感じているような。
- 小野島:
- それはご自分の意図されたことということで間違いないですか?
- 向井:
- 実際にマイクをそこに突っ込んでレコーディングしていますので、マイクが拾った音をそのまま再生しているんだなということですよね。でも、ちょっと出過ぎかなと。
- 小野島:
- これは『AK380』という今日の主催者であるAstell&Kernというオーディオメーカーのハイエンドなポータブルオーディオをリンデマンという小さいですけどすごく性能がいいアンプと、エラックという現代最先端のスピーカーを通して聴いてもらっています。機材を揃えればこれだけすごい音で聴けるということがわかっていただけたかなと思います。
 3. KIMONOS「Sports Men」(『KIMONOS』収録)
3. KIMONOS「Sports Men」(『KIMONOS』収録)
- 小野島:
- 向井さんの活動は、ZAZEN BOYSだけではなく、LEO今井くんと一緒にやっているKIMONOSというバンドもあります。その1stアルバム『KIMONOS』から「Sports Men」という曲を聴いてもらいました。普通にCDをリッピングした音を流しているんですけど、非常にいい音ですね。
- 向井:
- 曲自体は細野晴臣さんのカヴァー曲で、82年に発表された『フィルハーモニー』というアルバムに入っています。この曲が大好きで、そのトラック自体をほぼ完コピにしたいなと思って作ったんですね。『KIMONOS』自体が打ち込み主体の音なんですけど、音数自体はそんなに多くないんですよ。そんなに多くないんですけど、その中でこの「Sports Men」は音要素が多くて、バックグラウンドのシンセはずっとパッドでふぁーって白玉の音で埋め尽くされていたりしている。シンセベースもひとつのラインじゃなくて高い方と低い方の2階層になっています。つまり音数が多いわけです。これをいかにバランスを取るか、『フィルハーモニー』の細野さんの世界観に近づけていける感じにするかというバランス取りにけっこう苦労した曲なんですよ。
- 小野島:
- 音数多い割に曲がガチャガチャした感じは全然しない。むしろシンプルな印象を与える。
- 向井:
- 今聴くと確かに割れていますね。割れていますっていうのは音が割れているっていうじゃなくて、それぞれの要素がセパレートしている。
- 小野島:
- 分離がいい。
- 向井:
- これはこの『AK380』のパワーじゃないですか?
- 小野島:
- スポンサーケア(笑)。
- 向井:
- これはいただいて帰りますけどね(笑)。
- 小野島:
- 今、向井さんが言われた分離の良い聴きやすい音というのが、オーディオ的な観点から良い音とされることがあるんですけど、その良い音とカッコいい音って違ったりするんですよね。特にロックの場合は。このトーク・イベントはミュージシャンにとっての良い音を語っていただくのが趣旨なんですけど、でも実は良い音というのはミュージシャンによって千差万別であって、特に向井さんの場合は自分にとってカッコいいと思える音がいい音なんだろうなということがわかりました。それを追求されているというこだわりが強いんじゃないかなと、今のお話を聴いていると思うんですけど。
- 向井:
- そう、自分の好みですよね。
- 小野島:
- 自分の音楽をよりカッコよくするためにはどうしたらいいのか。それはいわゆるオーディオ的な観点の良い音とは違うかもしれないけど、でもこういうことをやることによって自分の音がよりカッコよく聴こえる、ということを追求されている。だから『SAPPUKEI』というアルバムもデイヴ・フリッドマンと組むことによって、ナンバーガールの音がよりカッコよく聴こえるようになった。特に今、良いオーディオででかい音で聴いてもらって、例えばパソコンのスピーカーから聴く音とは全然違う迫力があったと思うんです。向井さんはこの音を聴かせたかったんだなと伝わってきました。例えばデイヴ・フリッドマンのスタジオで向井さんが聴いていた音に近い音が聞こえたんじゃないかと思います。今日はありがとうございました。

小野島 大(音楽評論家)
音楽評論家。9年間のサラリーマン生活、音楽ミニコミ編集を経てフリーに。『ミュージック・マガジン』『レコード・コレクターズ』『ROCKIN' ON』『ROCKIN' ON JAPAN』『MUSICA』『REALSOUND』『週刊SPA!』『ナタリー』『CDジャーナル』などのほか、新聞雑誌、各WEB媒体などに執筆。著書に『NEWSWAVEと、その時代』(エイベックス)『音楽配信はどこへ向かう?』(インプレス)など、編著に『フィッシュマンズ全書』(小学館)『Disc Guide Series UK New Wave』(シンコーミュージック)など多数。オーディオに関する著述も多い。
https://www.facebook.com/dai.onojimahttps://twitter.com/dai_onojima

向井秀徳
1973年生まれ、佐賀県出身。1995年、NUMBER GIRL結成。99年、「透明少女」でメジャー・デビュー。2002年解散後、ZAZEN BOYSを結成。自身の持つスタジオ「MATSURI STUDIO」を拠点に、国内外で精力的にライブを行い、現在まで4枚のアルバムをリリースしている。また、向井秀徳アコースティック&エレクトリックとしても活動中。2009年、映画『少年メリケンサック』の音楽制作を手がけ、第33回日本アカデミー賞優秀音楽賞受賞。2010年、LEO今井と共にKIMONOSを結成。2012年、ZAZEN BOYS 5thアルバム『すとーりーず』リリース。今作品は、ミュージック・マガジン「ベストアルバム2012 ロック(日本)部門」にて1位に選ばれた。著書に『厚岸のおかず』
http://www.mukaishutoku.com/