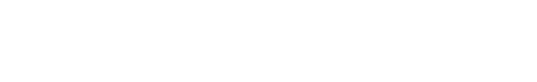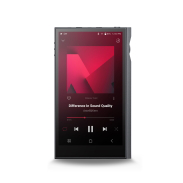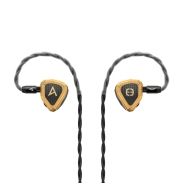PRODUCT MENU



 1. 「Technova」(『Future Listening!』収録)
1. 「Technova」(『Future Listening!』収録)
- 小野島:
- まず、94年発表の『Future Listening!』から聴いてもらいます。この作品を作ったときはどういう状況だったんですか?
- TEI:
- まだディー・ライトに在籍していたんですけど、体調悪かったんでのんびりしていて、カイロ・プラティックや指圧ばっかり通っていたんです。それでけっこうな費用になっちゃって、お金使っちゃったなーと思ってたときに、坂本(龍一)さんに「レーベルやるんだけどソロやらない?」って言われて、「いいとも!」って言ったんです。
- 小野島:
- (笑)。なるほど。
- TEI:
- 坂本さんのgutレーベルは日本ではフォーライフから、海外はワーナーから出ていて、僕が日本コロムビアに移籍したタイミング(2007年)では、結構レアな作品になってたんです。もう1回流通にちゃんと乗せましょうってことで、僕がマスタリング・スタジオへ行って、今までとっ散らかってたリミックスとかをまとめてCD2枚組にして、リマスター盤を出したんです。
- 小野島:
- 2007年ですね。やはり音がかなり良くなっていますね。
- TEI:
- そうですね。良くなってというか、ブラッシュアップしました。
- 小野島:
- ディー・ライト時代に坂本さんから声がかかったというお話ですが、ディー・ライトにいた頃に、すでに制作は始めていたんですか?
- TEI:
- そう。まだ脱退してなかったんですよ。調子悪くて、他のメンバーは3回目のアメリカ・ツアーに行ったけど、僕は行かなかった。実はこのアルバムに入っている「Technova」は、その頃に作ったんです。メンバーがツアーから帰って来たときに、歌が入る前の「Technova」とか、何曲か聴かせたんだけど、ピンと来なかったみたいで、「うーん……、ところでさ」って話変えられちゃって。結構凹んだんですよね。じゃあボツかなと思っていたんだけど、どこかで教授(坂本龍一)に聞かせたんですよ。91年にカセットテープに「Technova」って書いて、仲良い立花ハジメさんに渡して聞いてもらったんです。それからほどなくして、93年くらいにディー・ライトで稼いだお金が底を突いて。ほんと、マッサージに使い過ぎたんですよね。
- 小野島:
- じゃあもともとはディー・ライトでやるつもりだったんですか?
- TEI:
- はい、ソロになるつもりがまったくなかったんで。
- 小野島:
- その経緯を聞くと、ザ・ビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソンが、ツアーに行かないで、ひとりでスタジオにこもって『ペット・サウンズ』を作ったという有名なエピソードを思わせますね。それに近いような経緯が、TEIさんとディー・ライトにもあったということですね。
- TEI:
- そんなすごくないですよ(笑)。だけどぶっちゃけ、日本とロシアから来たDJ2人と、アメリカ人のヴォーカルの女の子(レディ・ミス・キアー)の3人組だと、やっぱり彼女のソロをみんなが聴きたがるのは自然なことだと思うし、僕ら(テイとDJディミトリ)は彼女がソロ活動をしようが、2人でチームとして動けばいいなと考えていたんです。その頃、クリヴィリス&コールっていたじゃないですか、C+C ミュージック・ファクトリーに。ジミー・ジャム&テリー・ルイスとか好きだったんで、2人でそういうプロデューサー・チームになろうぜって思ったんだけど、他の2人はいつまで経ってもツアーやり続けてるんです。もう十分アルバム売れてんじゃん、ツアーやっても売れないじゃんこれ以上、っていうくらい売れていたから。
- 小野島:
- それはミュージシャンの根本的な姿勢の違いですね。人前に出てライヴをやることに喜びを感じるミュージシャンって絶対いるわけだから。
- TEI:
- そうですね、普通ですよね。でも僕はそもそも、そんなものをまったく求めてなかった。ディー・ライトに入ってのも手伝いの気持ちでしたからね。
- 小野島:
- ふむ。でもDJディミトリとのプロデューサー・チームはかなり可能性ありましたね。
- TEI:
- うん。いっぱいオファー来ましたよ。言えないですけど、みんな知っているような人たちから。でも全部断りましたから。唯一受けたのが、坂本龍一さんと立花ハジメさん。もともと知っていた人、もともと中学生の頃に下敷きに写真を入れていた人たちからのオファー。自分なりの落とし前というか、これはチームじゃなくピンで受けようと。あいつらツアー行っているし、この機会をやってみるかと思ったんですよ。
- 小野島:
- そうして教授に誘われて、完成したのがこの『Future Listening!』という94年のアルバムですね。そこから話に出た「Technova」を聴いてください。
<『AK380』で再生中>
- TEI:
- こっちは日本盤だからフェードアウトしているけど、確かアメリカ盤はエンディングがあって、もうちょっとだけ長い。なんとなく変えなきゃなと思って。ちょっと違うんですよ、いろんなところが。
- 小野島:
- これはタイトルが「Technova」で、テクノ+ボサ・ノヴァ。
- TEI:
- あと、Novaって超新星って意味。新しい星と星がぶつかって新しい星が生まれることをNovaっていう。
- 小野島:
- ミクスチャーによって新しい音楽ができる、みたいな意味合いもある?
- TEI:
- そうですね。ディー・ライトでツアーしている間に、各地で時間があるとボサ・ノヴァのCDとか買ってたんです。CDってものを初めて買ったのがその頃だったと思うんですよ。手始めにアストラッド・ジルベルトとかから。
- 小野島:
- アナログじゃなくてCDで?
- TEI:
- そうそう、ツアー中はプレイヤーで聴けなかったんで、CDウォークマンを買ったんです。アストラッドのベスト盤とか、ジョアン・ジルベルトとか、アナログで持ってたけど。ベーシックな作品から聴き出したんだけど、だんだんもっと聴きたいなって思った時期だったんですよ、こういう音楽を。
- 小野島:
- なるほど。
- TEI:
- ブーツィがバンマスになって、フル・バンドのディー・ライトでツアーをやったんですけど、それで出演したのが91年の『ロック・イン・リオ』。ブラジルのフジロックみたいな、世界一大きいフェスらしいんですけど。それが2日間あって、そこでプリンスを観ました。僕の出る日はリサ・スタンスフィールドが出て、ディー・ライトがやって、この間亡くなったジョージ・マイケルという3組だったんですよ。それまで僕らは生演奏ではなくトラックを使っていたけど、ロック・イン・リオは予算が付いたので全部生演奏にしたんです。1週間くらいリハをやって。そのリハのときはお抱えシェフが3食作ってくれたんで、飯が美味くて。アメリカをツアーしてるとバターと塩とコショーの味しかしないけど、その時はポン酢とかもありましたからね(笑)。それで、そのライヴで僕はステージから落ちちゃって、マッサージ人生が始まるんです。
- 小野島:
- 災難でしたね。
- TEI:
- ステージが広すぎて、やることなくて暇な曲があって、ビデオでも録ってようと思って後ろ向きに歩いてたらストーンって落ちちゃった。入院して無事だったんですけど、むち打ちになって、朝病院に迎えに来てくれたのがなんとアート・リンゼイ。アンビシャス・ラバーズって、同じレコード会社だったんですよ。で、「俺アート・リンゼイ大好きやん」って思って、アートが「TOWAはレコ屋へ行きたいでしょ、一緒に行ってあげるよ」って言って連れて行ってくれた。むち打ちで、車で移動中も痛かったんですけど。ニューヨーク行ったらレコード貸してあげるからって、いっぱいレコード借りて、そこからモダン・ブラジリアン・ポップスとかMPBとか聴き出したんです。
- 小野島:
- じゃあ本場の大先生から直に。
- TEI:
- 先輩先輩、ブラジルの先輩っすよ。
- 小野島:
- ブラジルの先輩から直にボサ・ノヴァのレクチャーを受けたと。
- TEI:
- 今でもたまに会ったりします。数年前にもブルーノートで会いました。大人なんだけど、必ずギャーって余計なノイズを入れて。その余計がないと、ただのブラジル人、みたいな。アート・リンゼイ大好きです。
- 小野島:
- 温厚な優しい人ですよね。
- TEI:
- 初めて大ケガして、体調悪くて帰って来た時に、曲でも作ってみようかって思って作ったのがこの「Technova」とか、1曲目の「I Want to Relax,Please!」って曲だった。それでディー・ライトに聴かせたけど反応がなかったんで放っておいたんですけど、教授に尻叩かれて「やろう」と。それでアートに相談したんです。
- 小野島:
- ライヴのフィジカルなエネルギーみたいなものを吸収してガンガンに盛り上がっていたディー・ライトの2人と、ケガして休んでいたTEIさんとでは、そもそもテンションの違いはあるわけですよね。休んでいたTEIさんのテンションに見合った、ボサ・ノヴァっぽい、ラウンジっぽい音楽っていうのが、ディー・ライトの2人には全然ピンと来なかったっていうのは、なんとなくわかるような気がします。
- TEI:
- そうですね。結果的に、そのままアートの作品もたまに手伝ったりしましたけど。そこでチボ・マットの本田ゆかちゃんとも知り合ったりした。今につながる人たちとは、その頃から芽生えていて。91年くらいから。
- 小野島:
- 仮の話をしても仕方ないですけど、その時ステージから落ちなかったらどうなっていたんですかね。
- TEI:
- いや、どのみち落ちたと思うんです。あとで思ったんですけど、僕もうほんと辞めたくてしょうがなかったんです、ディー・ライトを。とにかくツアーを。だけど、ツアーだけやめるわけにはいかないし、はやく次(のアルバム)を作りたいなと思っていた。今日は色々端折って話していますけど、結論を言うと、たぶん守護霊が「落ちなさ~い」って後押ししてくれたんじゃないかと思うんです。そうやって体を壊して自分がダメになることでしか(バンドを)抜けられなかったですから、今思うと。スタッフ、照明とかPAとかいっぱいクルーいて、うちらの稼ぎで数か月食べていくっていう人たちがいっぱいいたんで。小心者だったし。そうでもしない限り、抜けられなかった。
- 小野島:
- 大きなアーティストってみんなそうですよね。社員が何百人もいるような会社みたいなもんじゃないですか。その稼ぎで食っている人がいっぱいいるから、自分ひとりの意志じゃなかなか決められない。
- TEI:
- そんな偉くないですけど。ソロになるってことは全然考えていなかったんですけど、流されて、というか。そのタイミングで、立花ハジメさんや坂本さんみたいな、もともと憧れていた人から、「一緒にやんない?」って言われたから。向こうからしたら鄭東和からディー・ライトのTOWA TEIに変わっていたわけだけど、僕としたらもともと憧れていた先輩なんで。彼らとだったらやってみようかな、っていう感じでやったんです。僕がヴォーカリストを探しているときにアートに曲を聴かせたら、何人か思いついた、と。彼はプロデューサーなんで。ライヴを観に行こうよっていって紹介されたうちのひとりが、ベベウ・ジルベルト。いい声だな、ピッタリだなと思って、すぐに「こういう曲あんだけど」って、楽屋で「Technova」の説明をして。あとで知ったんですよ、ジョアンの娘って。ボサ・ノヴァの神様みたいな人の娘なんです。
- 小野島:
- その時のTEIさんにとってボサ・ノヴァはヒーリング・ミュージック的なものでもあったんですか?
- TEI:
- そう。ブライアン・イーノのアンビエント・シリーズの3番にララージが参加していましたよね。そういうのも聴いて癒されていた。ハウスやヒップホップから1回離れて、インド音楽やサウンドトラック、ボサ・ノヴァやアンビエントを聴くこととか、そういう音楽を行ったり来たり聴くことを、自分の中で“Future Listening!”と呼んでいたんです。じゃあ、それで作ってみようって。ディー・ライトみたいにどの曲もダンサブルである必要はない。一番大きくアティチュードが変わった時期と言えるけど、作り出したら作り出したで自信がなかった。こんな音楽やってる奴どこにもいないし。
- 小野島:
- 誰が受け入れてくれるんだろうって?
- TEI:
- ピチカート・ファイヴの小西(康陽)さんはわかってくれるんじゃないかと思っていた。その頃仲良くしていたんで。ピチカートがアメリカに進出し出した頃、僕暇にしていたから、一緒にステージに出たんですよ。DJっていうか、立ってるだけみたいな。曲出したりとか。それで(野宮)真貴ちゃんとクラブ行ったりとか。それで真貴ちゃんもここに入ってるんです。
- 小野島:
- なるほど。言ってみれば、テイさんはポスト・クラブミュージックっていうのを模索している時期だった。いろんな事情があって、そういうのに疲れている時期にこういう音楽をやり始めたら、それがたまたま世界的なラウンジ・ミュージックの到来とか、そういう動きを先取りしたような形になった。これからこれが来そうとと思ってやったわけではなくて、TEIさんの個人的な事情や個人的な感覚から生まれたものがたまたま時代と合致した、と。そういうことですね。
- TEI:
- みたいですね。他人事のようですけど。ソロになってから特に売れたのがドイツとフランス。普通だったらアメリカの次はイギリスがマーケットになったりするけど、ドイツ人のメンタルにフィットしたのか、ラウンジ・ブームってことで、ドイツやフランスからお呼びがかかることが多かったんです。ドイツにDJで行ったら「Welcome」とか書いてあって、マスター・オブ・フューチャーリスニング、ゴッド・オブ・ラウンジ・ミュージックみたいなことも書いてあった。
- 小野島:
- なんかラリー・レヴァンみたいな言われようですね(笑)。
- TEI:
- でもその時、『Sound Museum』を作る前でブラコンしか聴いていなかったんですよ。トータルとかパフ・ダディとかの曲を全部2枚ずつ持って行って、イントロを繋いでかけたりとかして。みんなポカーンとしていて、いつボサ・ノヴァかかんだ!? みたいな。そういうギャップを感じましたね。
- 小野島:
- そうやって自分の感覚を基にして音楽をやっていると、人の期待に応えようというよりは、まずは自分の感覚っていうことですよね。
- TEI:
- そうですね。もうちょっとボサ・ノヴァやってれば、もうちょっと儲かったのかもしれないですけど。正直飽きっぽいんで、自分なりに『Sound Museum』っていうのを作って、ドラムンベースとかもハマったけど、『Last Century Modern』っていうアルバムはすでにあるジャンルのもの。『Future Listening!』に関しては混ぜようっていう意図が強かったですけど、それでも、まだクラブ・ミュージックのソサエティに属していたいって気持ちがあったんですよね。その中で、自分なりのカラーを出そうと。で、次に『FLASH』っていうアルバムが21世紀になってから出て(2005年リリース)。これも転機になったアルバムですね。どのアルバムも嫌いじゃないですけど。これも色々あった時期なんですよ。色々ありましたけど、やっぱり音楽が一番楽しいな、と。
- 小野島:
- 軽井沢に移住したのってその前ですよね?
- TEI:
- 2000年です。移る前に作っていたアルバムができたなと思ってたんですけど、引っ越したら気分が変わっちゃって、もうちょっと時間をかけちゃったんです。できたのがSWEET ROBOTS AGAINST THE MACHINEの『TOWA TEI』(2002年)。2005年に『FLASH』。その頃は東京との行き来で新幹線に乗ることが増えていて。乗っていると週刊誌を読んでる人とかいて、袋とじってあるじゃないですか、それをビリビリビリって破る音が「速い!」って思ったんですよ。閃光のような。見たらその雑誌が『FLASH』って書いてあったんですよ。「あ、これだ」と思って。音が速いというか、その前のアルバムにだらだら時間をかけちゃったんで、いかに早くアルバムを作るか、時給を上げられるかっていうことばっかり考えていました。そのあと色々あって『BIG FUN』(2009年)。今でも新幹線多いですけど、2000年からずっと東京に部屋は確保してます。部屋って言ってもベッドと机があって、Macをバンと置いて、Boseのラジカセがあって、そこにつないで作業を続けるだけなんですけどね。テレビも一応ありますけど。……あれ、何の話でしたっけ? 新幹線の話でしたっけ?
- 小野島:
- (笑)。『BIG FUN』です。
- TEI:
- ああ、そうだった(笑)。その時なりに自分のテーマとかコンセプトっていうよりも、マイブームみたいなものがあって、緩い縛りを自分で設けるんだけど、確かこの頃ハイハット使わないようにしていました。
- 小野島:
- それはなぜ?
- TEI:
- 高周波のチッチキチッチキっていう音に頼っているポップスが多いなと思って。YMOの『BGM』とか思い出したら、高域があまりなくて、中低域に重点を置いてたりとかってことを、なんか意識しましたね。『FLASH』の時からMacをノートブックに替えたんです。それまではタワー型だったから家でしか作れなかったけど、新幹線でも作れるように変わった。『FLASH』で自信を得て、「あ、できるどこでも」って感じになってきて、なんか自分に縛りをつけたかったんでしょうね。
- 小野島:
- なるほど。TEIさんの音楽はポップって言われることが多いと思うんですけど、巷に言うJ-POP的なポップとはちょっと違う気がする。何が違うんですかね?
- TEI:
- 街で流れているような? 僕の中では、音がキャッチーというか、聴いた数秒で「あ、あの人の音だ」っていうのがその人のポップスだってことですかね。ポップアップしているっていうか。たとえばCMの仕事も一時やりましたけど、テレビ番組のBGMにしても、ほんの数秒じゃないですか。イントロだけとか。音楽は勝ち負けじゃないですけど、立っているっていうか、そういうのはおもしろいなって僕は思うんですよ。
- 小野島:
- TEIさんの音楽って、テレビ番組のちょっとしたBGMとかにすごい使われてるって話を聞きました。何が理由なんですかね?
- TEI:
- 安心感? TEIとか使っとけばいいんじゃない? みたいな。まあ冗談ですけどね。でもそうなると良いですね。音響の専門学校とか行ってる人はとりあえず買いましょう! みたいな。これ使ってれば間違いないですよ、みたいな。この曲はクイズ番組で、この曲はスキャンダルのときに、とか。
- 小野島:
- TEIさんは名前を出さない仕事ってどのくらいやってらっしゃるんですか?
- TEI:
- そんなにやってないですよ、近年。自分のことやるか、ソロやるか、METAFIVEやるかなので。
- 小野島:
- 意識的に抑えているんですか?
- TEI:
- 日本に帰って来てわりとすぐに吉本興業に入って、7年間いたんですけど、わがままが利いたんです。僕を吉本に入れたいって言った当時のダウンタウンのマネージャーで、今社長になっている大崎洋さんから、「TEIくんおもしろいから来てえな」って言われて吉本に入ったんですけど、来る仕事を断ってばっかりいたんですよ。あんまり断ったら怒られるかなと思ったんですけど、「ええでええで、やりたくないことやんなくてもええ、かっこいいことだけやっててや」みたいな。そういう意味でラッキーだったというか。でも当時の社長は別の人だったんで。社長とトイレとかですれ違うと、「TEIくんが断った仕事は売れるね~」なんて言われちゃったりとかして(笑)。名前は出しませんけど、当時新人だった人をプロデュースしてくれとか、曲を書いてくれとかいっぱいあったんですけど、本当にやらなかったですね。でも、手がけた作品の打率は高いと思います。
- 小野島:
- ふむ・ブライアン・イーノがウィンドウズ95の起動音やったとか、そういう、名前は出ないけど誰もが聴いたことのあるような音楽ってあるじゃないですか。たとえば駅のホームで流れてるような音楽。あれもちゃんとした作曲家の人が作っているわけなんだけど、決して名前は出ないっていう。そういう仕事に興味ありますか。
- TEI:
- ああいうものはやりたいですね、仕事的には。極端な話、歌唱力のない人をプロダクションでうまく聞かせるとか、ダンスチャートに入るような曲を、っていうようなオファーが(当時は)多かった。あまりやらなかったですけどね。(突然)最近思うのは、朝飯食ってるときの音楽がひどい。ジャズとかクラシックかけとけば良いでしょ的な。
- 小野島:
- ホテルとかで?
- TEI:
- そうそう。クラシックでもいろんなクラシックあるじゃないですか。激しすぎとか、ジャズでもモーダルみたいな。朝飯っぽくねーな、みたいな。
- 小野島:
- 不安にさせるような音楽ですね。
- TEI:
- そうそう。急いで食べないとまずいぞ、みたいな。
- 小野島:
- そろそろ曲行きましょう(笑)。『BIG FUN』から「A.O.R.」をお聴きください。
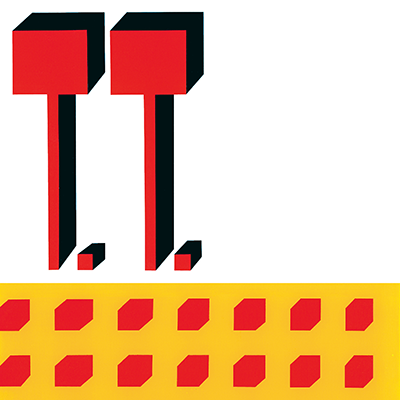 2. 「A.O.R.」(『BIG FUN』収録)
2. 「A.O.R.」(『BIG FUN』収録)
<『AK380』で再生中>
- TEI:
- 思い出しました。この曲はもともと、携帯の中に入る音としてインストで作ったもので、気に入ったから歌ちょっと入れようかなと思ってたんです。ヴォーカルは太田莉菜ちゃん。その後松田龍平くんと結婚した。ばったりバーで会って、彼女がロシア語できることを知って、そういえばロシア語やったことないなと思って。友達と家においでよって誘って、みんなで家に来て、家で録ってましたね。
- 小野島:
- なるほど。そろそろ新作『EMO』の話もしましょうか。
- TEI:
- METAFIVEっていう流れに身を任せてというか、バターで嫌な思いをしたディー・ライトっていうグループ以来、まさかの49歳にしてバンド活動が始まって、最初は(高橋幸宏の)バック・バンドだったんですけど、6人でMETAFIVEになり、去年はアルバムも出しました。そのちょっと前から、前作の『CUTE』が終わって何曲か始めたりしていたんですけど、METAFIVEで中断したりして。でもMETAFIVEも、言ってみれば1人2曲でアルバムができちゃったりするじゃないですか。なので、METAFIVEで自分のやること終わったら、こっそりソロを作ったりしてたたんです。今回は後半になってMETAFIVEの人たちもいっぱい入ってくれて。
- 小野島:
- 小山田くんとか、3曲でギター弾いていますよね。
- TEI:
- 最初は何も考えずに直感で作るけど、そろそろどういうパッケージになるんだろうってなったときに、9枚目だし、まず9曲にしようと。もうちょっと曲は作ったんですけどね。それでいろいろバランスを考えるうちに、もうちょっとインスト増やそうとか、女の子(のヴォーカル)を増やしたいなってなってきて。お寿司食べるときにガリも食べたいみたいな。カレーも良いけどシチューもね、っていう(笑)。
- 小野島:
- (笑)はい。
- TEI:
- それで次にお聴かせする曲は、だらだら時間をかけ過ぎた曲です。自分で出来が良いなとか、結果的に多くの人に気に入ってもらえたりする曲って、意外とはやくできる曲が多いんですけど、この曲は近年稀に見る長さというか、だらだらと、3.11のあとくらいから作り始めて。ずっとやってるわけじゃないですよ、途中諦めたり、やっぱやめた、もう1回やってみよう、とか。すごくたくさんヴァージョンがあるんですけど。プリンスが亡くなって、急に歌ものにしようと思ったんです。それまではインストだったんですけどね。で、ヴォーカルを誰にしようと思ったときに、ゆるめるモ!のあのちゃんっていう女の子にお願いした。プリンスとは全然関係ないんですけど。
- 小野島:
- なぜプリンスを聴いて、アイドルを起用しようと?
- TEI:
- 「あのトラック歌ものになるな」って思い出して。プリンスとか歌ったらかっこいいだろうなと思ったんですよ。この歌メロじゃなくて、プリンスのメロディでというか、プリンスらしく歌ったら、この曲はかっこよくなるだろうなと思って、それで眠っていた曲が敗者復活したわけですよ。
- 小野島:
- なるほど。
- TEI:
- でもそれじゃいかんだろ、と。プリンスをなぞっても意味がない。誰だろう。バランスを見たときに、女の子が足りてないなって思ったんです。で、UAみたいに歌のうまい子を録ったばっかりだし、歌唱力じゃなくて、個性がある人、それも若い子がいいなって。METAFIVEが年寄り多いからね。それで自分の子供くらいの人に頼んだんです。
- 小野島:
- それが今から聴いていただく『REM』です。アルバム発売は3月22日なので、本邦初公開ですね。
- TEI:
- これは96kHz/32bitで、作ったままの環境で聴いていただきます。
 3. 「REM」(『EMO』収録)
3. 「REM」(『EMO』収録)
<『AK380』で再生中>
- 小野島:
- TOWA TEIの3月22日発売『EMO』から「REM」。ヴォーカルがゆるめるモ!というアイドル・グループの、あのという女の子。ベースがBuffalo Daughterの大野由美子さん。フリューゲル・ホルンはMETAFIVEの権藤知彦さん。ミックスはGoh Hotodaさんです。
- TEI:
- 宇多田ヒカルの元エンジニアの方ですね。
- 小野島:
- クラブ・ミュージックにかけては第一人者ですね。マスタリングはMETAFIVEの砂原良徳さん。まさにオールスターキャストという感じですね。
- TEI:
- この曲は、近年では珍しく長くだらだらと、ボツかなと思いながらも粘って、やっと出せる域に達した珍しいトラックなんです。そういうのって結局あんまり気に入らないんだけど、これは、僕は結構気に入っている。アルバムの中でもこういう曲は全然ないので。
- 小野島:
- 聴いていただいてわかると思うんですけど、低域がすごいじゃないですか。この低域をちゃんと再生できれば、あなたの家のオーディオはかなり優秀ですよ、という。オーディオ・チェック用にも最適。
- TEI:
- 「A.O.R.」は実はいろんなことが功を奏して上手くいったミックスだなと思っていたら、若いエンジニアとかがリファレンスとして使うって言ってるんですよ。自分のミックスと「A.O.R.」と聴き比べて、ローとかハイとかバランスを調整していくそうです。自分としても満点に限りなく近いミックスができたと思いますね。
- 小野島:
- ふむ。個人的には前の『CUTE』もすごく音が良かった。もちろん音楽の内容も良かったし、音の良さっていう点でも素晴らしかった。でも、たぶん今回のアルバムが、過去のTEIさんの中で一番音が良いんじゃないですか?
- TEI:
- 最新作ですし、そうであってほしいですね。
- 小野島:
- 96kHz/32bitで録ったってお話がでましたけど、それは具体的にどういう過程をたどって?
- TEI:
- METAFIVEでやるときにメンバーでいろんな意見があったんだけど、投票して多数決で、48kHz/24bitで作ろうってことになってたんです。96kHzでやってる人もいたけど、僕とLEOくんはそれまで44kHzでやっていて、じゃあ間を取って48kHzでやろうということになった。今回のアルバムも48kHz/24bitで作っていたんです。Gohさんいわく「48kHz/24bitはTEIさんの音楽に合ってると思うんだけど、(ミックス用に)書き出すときに96kHzにすれば良かったね」と。それはなぜかというと、彼がプラグインとかを使ってミックスするときは、32bitの48kHzや96kHzでやるんだけど、それは96kHzでやったほうがエフェクターの乗りが良いし、艶が出るからだって言うんです。
- 小野島:
- ああ、なるほど。
- TEI:
- そう言われたものの、結果的には96kHzで書き出していたらたぶんうまくいかなかったと思う。他の曲で(48kHzで)80トラックくらい使ってる曲があって、その曲を作業してるときだけいつもMacが落ちたんですね。メモリが足りなくて。だからそれを96kHzにしていたら無理だった。結果的に48kHz/24bitで良かったんですね、渡すときは、って。それで、Gohさんは48kHz/24bitで僕から受け取ったものを、48kHz/32bitの環境でミックスしました。たまにMac落ちたりしながら。
- 小野島:
- ふむ。
- TEI:
- それで砂原くんにどうやって渡そうかっていうときに、彼はStudio Oneっていう音楽制作ソフのを使ってる、あれって音良いよねって話になって。ならマスターは96kHz/32bitで、Studio Oneをレコーダーにして作ろうと決めたんです。そのまま砂原くんが開けるようにしましょうと。ただモニター上ではずっと48kHz/32bit環境で聴いてミックスをしてたんで、48kHz/32bitでマスターも用意したんですよ。そうしたら砂原くんは96kHz/32bitを使って、アナログ用のマスターとCD用のマスターを作ったんです。アナログ用のマスターは96kHz/32bitのまま納品して、アナログ盤を出す。ハイレゾにするときは、これからハイレゾの配信サイトの人と話して、24bitにコンバートするのか、32bitのままでいけるのかっていう話をしなきゃいけないんですけど、今日は96kHz/32bitで砂原がアナログ用にマスタリングを加えたものを聴きました。
- 小野島:
- なるほど。今回のアルバムの『EMO』というタイトルや、込められたテーマについては公式サイトのインタヴューに詳しいので(http://www.towatei.com/emo/interview/)、そちらを参照していただくとして、最近テイさんはどういう瞬間にエモいと感じますか?
- TEI:
- コメント書いてくれって言われて『LION/ライオン ~25年目のただいま~』っていう映画を観たんですけど、これはまさにエモい映画でした。インドの5歳の子どもがお兄さんとはぐれてロスト・チルドレンになっちゃって、オーストラリアの家族に育てられて、とても優秀な若者に育つんだけど、あることをきっかけに、会えなくなっていた家族に会いたいって思うようになるんですよ。それでGoogle Earthを使って家族の居場所を調べるという話。テクノロジーがそういうエモーションを手助けするというかね。僕はやっぱりそういうところにエモさ感じる。クラフトワークは冷たい無機質な音楽とか言われている時代じゃないんで、もう。テクノロジーを使った音楽でも自分なりのエモさは出せるよ、と。イエスみたいにいっぱい転調とか大げさな展開とかしなくても、大サビとかなくても、エモくなれるよっていうことですね。自分なりに。
- 小野島:
- テクノもジャーマン・プログレも、かつては単調な機械的で非人間的な音楽と捉えられてましたよね。昔だったらコンピューターが作る音楽なんて非人間的で聴けたもんじゃないって、まじめに論じられていた時代もあった。
- TEI:
- サンプラーが出てきて、イギリスの音楽組合の人たちが「音楽がなくなる」とか言って訴えたりしていましたよね。
- 小野島:
- そういう時代もあったんだけど、機械が作った音楽だってちゃんと感情も込められるし、人間の意図みたいなものもそこにちゃんと焼き付けることができるっていうことを、だんだんみんなわかってきた。むしろ機械を通すからこそ人間味が増すというか、そういうふうなこともあるのかもしれないなって気がしますね。
- TEI:
- メロディとかヴォイシングとかももちろん大事ですけど、リズムとか音響とか、さっきのロー(低域)とか、そういうことでも表現はできると思う。全部が合わさったうえでね。でも結局僕は、激しくなくていいんですけど、電流が流れる程度にエモーショナルにならないと、物を作っていくうえで推進力にならないんですよね。眠い曲できちゃったな~眠い時期だったんで、こういう曲しかできないなと最初は思ったんですけど、眠い曲ええやんっていうか。9曲中1曲だけでも、眠たい曲作ろうって思ったりとかね。“EMO”っていう括りでいいかなって思ったら、そういう曲もOKになった。クマンバチって曲もあってもいいし。でももっとアップテンポで明るい曲もありますよ。METAFIVEのみんなとやってるようなね。
- 小野島:
- こういう感じでアルバムも完成されまして、実は、今年1月に入ってから、TEIさんの軽井沢のお宅にお邪魔しました。ご自宅のスタジオの音も聴かせていただいて、このアルバムも聴きました。軽井沢って今も雪がガンガン降っていて、新幹線で高崎の次が軽井沢なんですけど、高崎までは東京と同じなんですよ。雪も何も降ってないんだけど、一駅越しただけでそこは雪国だった。まさに川端康成の世界。駅から車で20分くらい行ったところの別荘地に、TEIさんのお宅があるんですけど、本当にあたり一面雪景色だった。雪って音を吸うから、すごく静かなんですよ。その静かなで真っ暗な中に、TEIさんのお宅だけ煌々と照っているっていうすごく幻想的な風景で。家の中から見ると、外は当然雪景色。そういう中で作っているからTEIさんの音楽ができるんだなって、実感できました。TEIさんの音楽の中にある、言葉を選ばないで言いますけど、ある種の清潔さっていうか、そういうものは、そこから出てるのかなっていう気がなんとなくしました。
- TEI:
- 僕にとっては、今やあれが日常なんですよね。
- 小野島:
- そう、TEIさんにとっては日常なんだけど、我々にとっては非日常なわけですよ。東京に住んでいる者からしたら、雪景色なんてまさに非日常の極致で、そんな中でこういう音楽を作っていたら、それは東京のど真ん中、繁華街のど真ん中で作っているのとは、全然違うものができるんだろうなって、容易に想像がつくというか。
- TEI:
- 東京育ちだったんで、ここ新宿にもよく来ました。品川育ちだったんで。そこに、正直、作り手としては限界を感じるようになったんですよね。年とともに。
- 小野島:
- 余計なものがないっていうかね。雪が降ることによって、いろんなのが全部覆い隠されるみたいに、TEIさんの音楽も、いろんな雑多な情報みたいなものが、全部覆い隠されて、あるいは排除されて、こういうきれいな音楽ができたんだなと私は思います。
- TEI:
- そういうことにしましょう(笑)。アルバムの補足的に、今日話しきれなかったようなことを小野島さんに話を聞いてオフィシャルのインタヴューとか、特設サイト上で掲載していきますので、そちらもぜひ。今日はありがとうございました。

小野島 大(音楽評論家)
音楽評論家。9年間のサラリーマン生活、音楽ミニコミ編集を経てフリーに。『ミュージック・マガジン』『レコード・コレクターズ』『ROCKIN' ON』『ROCKIN' ON JAPAN』『MUSICA』『REALSOUND』『週刊SPA!』『ナタリー』『CDジャーナル』などのほか、新聞雑誌、各WEB媒体などに執筆。著書に『NEWSWAVEと、その時代』(エイベックス)『音楽配信はどこへ向かう?』(インプレス)など、編著に『フィッシュマンズ全書』(小学館)『Disc Guide Series UK New Wave』(シンコーミュージック)など多数。オーディオに関する著述も多い。
https://www.facebook.com/dai.onojimahttps://twitter.com/dai_onojima